■出産後のマネー
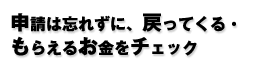
Introduce
規定の手続きをすれば、出産後に戻ってくるお金があります。忙しいママに代わってしっかり申請をしておきましょう。雇用形態や企業によって違いがあるので自分の場合はどうなのか、夫婦の条件を合わせて確認しましょう。
⇒「ワーキングママがもらえるマネー、
払わなくていいマネー」
(自営業や専業主婦は対象外になります)

「子育て参加」や「ママのサポート」だけじゃない、自分が主役の「父親の子育て」って意外と簡単で面白い!育児のダイゴミを知って本物の「かっこいい」父親になるために、「電子父子手帳」でたくさんのヒントを発見しよう!
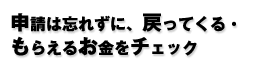
Introduce
規定の手続きをすれば、出産後に戻ってくるお金があります。忙しいママに代わってしっかり申請をしておきましょう。雇用形態や企業によって違いがあるので自分の場合はどうなのか、夫婦の条件を合わせて確認しましょう。
⇒「ワーキングママがもらえるマネー、
払わなくていいマネー」
(自営業や専業主婦は対象外になります)
健康保険(国民健康保険か会社の健康保険、公務員は共済組合)に加入している人は全員もらえます。
額は最低で35万円。勤め先によって「付加金」がつく場合があるので人によっては「35万円+α」になります。
※ 妊娠4ヶ月以上(12週以上)の死・流産の場合も支払われます。
胎児数分だけ支給されるので、例えば双生児の場合なら出産育児一時金は2人分になります。
※ 妊娠4ヶ月以上(12週以上)の死・流産の場合も支払われます。
用紙は事前に会社か役所でもらっておき、産後入院中に病院が記入する欄はお願いしておきましょう。その後なるべく早く会社に提出しましょう。出産の翌日から2年以内ならば請求できます。これ以上経過すると請求資格を失いますが、早く手続きをすれば振り込みも早くなります。(通常早くて2週間位、遅くても2ヶ月後までには指定した銀行口座に振り込まれます。)
●専業主婦の場合
パパが会社員の場合=パパの会社の健康保険(職場、または社会保険事務所へ)
パパが自営業の場合=パパの国民健康保険(役所の健康保健課へ)
●会社退職をした場合
パパが会社員の場合=パパの会社の健康保険またはママの会社の健康保険
パパが自営業の場合=パパの国民健康保険
※退職後6ヶ月以内に出産した場合ママの健康保険でもOKです。
ただ出産時にはパパの扶養なのでパパの健康保険で手続きを
●退職後保健を任意継続または会社員として仕事を継続した場合=ママの会社の健康保険
●自営業、パートとして仕事を継続した場合=ママの国民健康保険(ママの年収130万円以上) ※働いていても年収130万円未満なら専業主婦と同じ
1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超える場合に確定申告すると税金が戻ってきます。(2年にまたがるものは別々に。年ごとに申告をしましょう)
(1月〜12月に家族全員が支払った医療費の合計)
−(出産一時金や生命保険の入院・給付金など受取った金額)
−(10万円 ※全員一律)
=(医療費控除の対象額 ※これが全額戻るわけではありません)
 ○認められるもの
○認められるもの手間の割には少ないという声もありますが、これによって所得が下がるので、翌年度の住民税が安くなる(前年の所得を元に決定するので)というメリットがあります。
普段から家族全員の医療費のレシート、領収書を集めておきましょう。交通費など領収書のないものはノートに日付け、病院名、支払った金額を忘れずに書いておきましょう。
※翌年1月初旬〜5年以内に申告用紙(会社員は還付申告)を税務署か役所でもらいましょう。
(頼めば郵送も可能です)
※申告用紙、領収書やノート、源泉徴収票などを持って税務署で申告します。
体重が2000g以下で身体の機能が十分でないまま生まれた赤ちゃんが指定医療機関で入院治療を受ける場合、所得に応じた援助がうけられます。(対象年齢は1歳未満)詳しくは保健センターへ。
小学校3学年修了前の子供(9歳到達後の年度末まで)を扶養する世帯主の前年の所得(給与所得控除後の金額)と扶養家族数によって、もらえるかどうかが決まります。
| 会社員・公務員(厚生・共済年金) | 自営業・自由業(国民年金) | ||
|---|---|---|---|
| 扶養人数 | 限度額 | 扶養人数 | 限度額 |
| 0 人 | 460万円未満 | 0 人 | 301万円未満 |
| 1 人 | 498万円未満 | 1 人 | 339万円未満 |
| 2 人 | 536万円未満 | 2 人 | 377万円未満 |
| 3 人 | 574万円未満 | 3 人 | 415万円未満 |
| 4 人 | 612万円未満 | 4 人 | 453万円未満 |
| 5 人 | 650万円未満 | 5 人 | 491万円未満 |
| 6人以上 | 以降38万円ずつ加算 | 6人以上 | 以降38万円ずつ加算 |
第1、2子は月額5000円・第3子以降は月額1万円
申請のあった翌日からの支給(2月、6月、10月に指定口座に入金)です。さかのぼっては支給してもらえないので、早めに手続きしましょう。(なるべく生後15日以内に)
印鑑、年金加入証明書、口座番号、転入者のみ所得証明書
健康保健に加入している乳幼児に対して各自治体が、保健がきく医療費の全額または一部を負担してくれるという制度ですが、対象年齢や内容、条件など自治体によってまちまちです。
出産前に役所に内容や必要書類を確認し、産まれたらすぐ赤ちゃんを健康保険に加入させましょう。

自治体によって、病院で医療証を見せるだけで無料、または一部負担になるケースと、その場では一旦支払い、後日1ヶ月分まとめて役所に申請すると(書類を提出する)、その後指定した口座に振り込まれるケースがありますが、後者の場合申請を忘れるとそれっきりなので注意しましょう。
身体の障害を指定医療機関で入院治療、手術を受ける場合所得に応じた援助がなされます。また身体障害者手帳が交付されると松葉づえ、補聴器などが給付されます。詳しくは保健センターへ。
18歳未満の子供の慢性疾患に治療について公的援助があります。詳しくは保健センターへ。
悪性新生物(がん)、慢性腎疾患、内分泌疾患、ぜんそく、慢性心疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患